地域医療・プライマリーケア 一般社団法人 地域医療教育研究所
本研究所の基本理念
【2026年度地域医療教育研究費・研修事業助成金の公募について】
助成事業実施にあたって
一般社団法人地域医療教育研究所は、将来医療を通して地域貢献したいと志す学生への実習先の紹介・旅費補助、学生・研修医・保健医療福祉職員向けのセミナーの開催、地域住民や行政・地域ケア担当者に対する健康的なまちづくりへの提案や啓発活動を行ってきました。
今年も地域医療教育に関する研究者、また地域協働ケア推進のための研修企画者に対し助成を行うことといたしました。多数の応募を期待しております。
【目的】
この事業は、医学部学生、研修医、専攻医等に対して、医療機関が地域住民・行政・福祉法人等と協働する活動をどのように教育することが成果を得やすいかについて研究する個人あるいは団体に研究費を助成する。また、多職種協働による地域ケアネットワークづくりの企画や調整を行うケアマネジャーなどの研修に対し研修事業費を助成する。
①地域協働プライマリケア教育研究事業
医学部学生、研修医、専攻医に対して、医療機関が地域住民・行政・福祉法人等と協働する活動をどのように教育することが成果を得やすいかについての研究
②地域ケアマネジメント研修事業
多職種協働による地域ケアネットワークづくりの企画や調整を行うケアマネジャーなどに対する研修
【募集期間】
2026年1月1日から2026年3月31日まで
【事業実施期間】
2026年7月から2027年6月までとする。
なお、従来からの継続事業及び新規事業を対象とする。
※地域医療教育・研修基金、地域医療教育・研修事業助成金申請書類はこちらよりダウンロード頂けます。
※ 過去の助成対象事業の研究結果は以下の通りです。
<2023年度助成対象事業>
実施期間:2023年9月1日〜2024年8月31日
・地域多職種協働実習に関する研究事業
申請者:茨城県立医療大学 安江憲治助教
【事業目的】
地域医療に携わる将来の保健・医療・福祉の分野を支える、高い資質と豊かな人間性をもった看護職、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師などの医療専門スタッフ育成および地域医療教育の活性化。
※ 研究成果は下記リンクからご確認頂けます
・地域協働ケアナース養成事業
申請者:旭川市立大学 羽原美奈子教授
【事業目的】
北海道の地方部で診療業務に従事するだけでなく、地域の多職種および住民と協働できるナースを養成し、地域共生社会の構築に貢献する。
※ 研究成果は下記リンクからご確認頂けます
<2024年度助成対象事業>
実施期間:2024年7月1日〜2025年6月30日
・地域多職種協働実習に関する研究事業
申請者:茨城県立医療大学 斎藤瑛梨助教
【事業目的】
本事業を継続することで、質の高い地域医療活動実践ができる専門職を養成するための基盤を築き地域医療の発展に寄与する。本事業の成果として学会発表や論文発表、学生主体で作成する冊子をホームページで公表する予定。
※ 研究成果は下記リンクからご確認頂けます
<2025年度助成対象事業>
実施期間:2025年7月1日〜2026年6月30日
・札幌市立大学看護学生コンソーシアム事業
申請者:札幌市立大学看護学部 金久保秀斗
【事業目的】
本事業は、看護学生がボランティアとして地域に出向き、健康教室等の活動を通じて地域全体の健康・福祉の向上に寄与することを第一の目標としている。また、上記の活動を通じて得た学びや新たな知見を、学生主体の「看護学生コンソーシアム」として、北海道内の病院で他職種を交えたシンポジウムを開催し、交流を深めることで、将来即戦力となる医療人材の育成に繋げるもの。
※ 研究成果については後日当HPにて公開させて頂きます。
第3弾 夕張の医療を考える集いを開催しました
第3回 夕張の医療を考える集い
テーマ:「この町で生きるために~食と医を考える~」
日 時:2024年5月18日(土)14:00~16:00
会 場:日本キリスト教会夕張教会(夕張・鹿の谷1-61)
主 催:「夕張の医療を考える集い」(代表:前沢政次)
共 催:一般社団法人 地域医療教育研究所
参加者:19名
司会:渡辺輝夫(市民、牧師)
「夕張の医療を考える集い」は、昨年講演中心の集いを2回もったが、今回は診療所移転やスーパーが閉店し、生活面での不便さを増した本町地区に住む者が、安心してこれからも暮らしていくために、どのような課題があるのか、率直な声をあげ、話し合いをしていきたい。
発題Ⅰ:前沢政次(前夕張市立診療所医師)
夕張市立診療所で月一度(月曜)午前診療、午後訪問診療にあたっている。その立場から診療所の現況について報告。宮城で次のような事例を経験した。薬を飲むのを忘れたり、食事を摂るのを忘れてしまう84歳の認知症女性の受け容れをどうすべきか。家族(娘)は施設入所をすすめたいが、本人は家で暮らしたいという。前沢から<施設に入ったら長生きできるというものではない。本人がしたいならそれを優先し(あるがままを受け容れる)それを支える(見守る)のが医療関係者。もしかしたら正解は一つではない。ベストはない。悩みながら、あえて答えは出さずに見守ること>を提案した。
協議Ⅰ(発言の主なもの)
・診療所の対応はものすごく親切になった。ただ、診療科目に毎日ないものがある。
いままでは「共同購入」を中心に、足りないものを「かね安」で買っていたが
それがなくなって困っている。近くのアパートの住人は特に困っていると思う。
シルバー人材センターが今期で閉鎖になり冬の除雪が大変だ。
・日常品で急に必要な時に困る。
・移動販売車が来ない。
・「来ない、来ない」と言ってないで働きかけが必要だ
・車に乗らない者や手離した者が利用するデマンド交通は前日まで予約しなければならない。
急に必要な時予約しないで乗れる方法はないのか
・親の介護で札幌と夕張を行き来している。緊急の場合、車を運転しないのでどうしたらいいか。
それなのに10月から中央バス(札幌直行)がなくなる。検査キットが夕張にないときどうしても
札幌に行かなければならず、親戚中に電話して頼んだことがあった。
・行政側もいろいろ検討はしている。札幌まで直行できなくとも北広島まではどうかなど。
・できない時はケアマネジャーに相談してみたらどうか。自分で抑えこまないで行政に相談して
みるとか。なんでも自分でしなくてはと考えない。
・豊生会のバスを利用したことはある。社協がバスを出すのではないか。介護タクシーや本当に
緊急の場合は救急車を要請するなど。
・札幌の教会のある町内会の75歳以上の独居は80世帯。なかなか外に出てこない。
教会に移動販売車が止まるよう働きかけてからようやく買い物に出てくるようになった
(買い物難民)。
移動販売車も物資の供給ができることが必要。物資のネットワークと人の移動のネットワーク
の必要
発題Ⅱ:武藏学(天使大学名誉教授)
大正期より人口一万人で推移している町の出身で6年後財政破綻が想定されているので夕張のことは他人事ではない。町立病院が一つあり内科だけ毎日、外科は隣り町で対応するという協力体制をとっている。昨年102歳で父が亡くなったが、改めて人はいつか死を迎えるがそれは淋しいけれども慰めでもあると感じる。
今まで医療側は「長生き、長生き」をはかってきたが、医者がやることは限られている。それまでに、自分の最期をどう迎えるか家族や医療者に<文書>で伝えておくことが大事である(札幌豊平教会リビングウィルを例にあげて)。さらに国(厚労省)は積極的にかかりつけ医を中心にして本人の将来に向けたケアを実践していくよう促している(地域包括ケアシステム)。これは国民としての<権利>である。
もうひとつ、孤独死・孤立死の問題がある。最近(5月14日朝日新聞)、年間の孤独死は推定で6万8千人になるということが公表された(警察庁)。これには集まって交流を深めていける<居場所>が大事である。またそれを見守る住民ネットワークが必要。
大事なのは、一番必要に迫られているところが案を作っていく以外にない。「夕張モデル」を作って行くことが、日本、そしてこれから高齢化社会を迎えるアジアのためになる。
協議Ⅱ
・昨年夫を亡くしたが、元気なうちにリビングウィルを書いておいて良かった。突然倒れ延命措置をするか、死後解剖するかなどをお医者さんから尋ねられたが大きな動揺はなかった。きのうきょうのことではパニックになったに違いないと思う。
札幌に住んでいるからといって決していいことだけではない。どこの病院に行ったらいいか分から ないのが現実。自分で判断することが大切。
・今回の集いは二つあったと思う。「人間の死」「夕張の行政」。教会での集会なのにあまり宗教臭くなくていい。死とは本来あるべきこと。孤独死については社会的に防げる仕組みをつくることが大事。「夕張モデル」を目指すとしても気軽にためしてみることが大事である。<トライ&エラー> 自分で買い物をすることも大事だと思うのでそのような交通システムをつくることが必要。このような集まる場所も必要。
・更年期の女性の診察に従事しているが、40~50歳代もおじいちゃん・おばあちゃん世代と子どもの間で、さらに仕事を抱え大変な思いをして生きている。
・「かね安」閉店後、若い世代が地域コミュニティーをつくるという思いでもう一度再開しようとしていることをお知らせしたい。そのとき、必要なのは積極的に<参加すること><行くこと>だと思う。
まとめ
同じ境遇の人たちの居場所(ネットワーク)を小さくともいくつもつくっていくこと
<遠くの親戚より近くの他人>
新着情報
【令和6年能登半島地震で被災された皆様へ】
この度の令和6年1月1日石川県能登半島地震により、尊い命を奪われた方々のご冥福をお祈りいたします。
また被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。特に地域医療を守ってこられた医療機関の再開・復興をお祈り申し上げます。
前沢政次
【書籍のご案内】
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
2022年6月25日に当法人代表理事前沢政次の著書「大人になる前に知る老いと死」が発行されました。
本書は老いによる体と心の変化や認知症、家族とのお別れなど「老い」と「死」をめぐる5章から人生の意味や価値を考える1冊となっております。
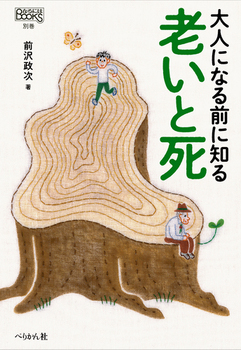
書籍概要タイトル:大人になる前に知る老いと死
著者名:前沢 政次
発売:2022年6月25日
価格:1,600円+税
発行:ぺりかん社
全国の書店若しくはこちら↓↓↓からお求め頂けます。(クリックすると表示されます)
会員募集
一般社団法人地域医療教育研究所の会員になって、一緒に活動を支えてくれる方を募集しています!
◇入会資格
(1)正会員 当研究所の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)準会員 当研究所の目的に賛同して入会した個人で入会金が免除された方
(3)賛助会員 当研究所の事業を賛助するために入会した個人又は団体
◇会 費
| 入会時 | 年会費 | |
| 正会員 | 個人 10,000円 法人 200,000円 | 個人 5,000円 法人 100,000円 |
| 準会員 | ― | 個人 5,000円 |
| 賛助会員 | 個人1口 5,000円 法人1口 100,000円 | ― |
◇申込み
「氏名」「住所」「連絡先」を、メールまたは電話・FAXでお知らせください。
当研究所から入会申込書を送付いたします。
お問合せ・ご相談はこちら
(よつば会計事務所内)
一般社団法人地域医療教育研究所の公式ホームページにようこそ。
当研究所は地域医療教育をライフワークとする北海道大学名誉教授・前沢政次が代表理事を務め、地域医療をめざす学生への実習先の紹介・旅費補助、学生・研修医・保健医療福祉職員向けのセミナーの開催、地域住民や自治体への健康的まちづくりの提案や啓発活動を行っています。
基本理念は地域協働型プライマリーケアです。
当研究所について
医療政策に関わる支援活動
一般社団法人
地域医療教育研究所
住所
〒001-0010
北海道札幌市北区北10条西1丁目1−1
